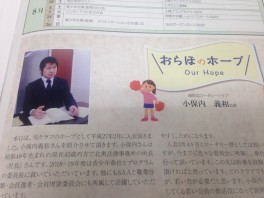岩手に戻った翌年である平成17年から現在まで、毎年、お盆期間中の特定の日に「朝から来い」と言われ、晩まで滞在することを余儀なくされています。
これは、私の実家など(地域内で昔から生活する特定の人々?)に地元で親交の深い(神葬祭の関係で付き合いのある?)家々同士(15~20軒ほど?)が、お盆の特定の日に互いの家庭を訪問して神棚を拝んで廻るという習慣が古くからあり、兄(存命中は父も)が他のご家庭を訪問するため、その間、私に実家に滞在して訪問客に挨拶せよ、と命じられていることに基づくものです。
といっても、中学卒業と同時に実家を出て遠方で長く暮らした私には、地元の方々とのお付き合いは(子供の頃にお世話になり現在もご健在のごく僅かな方などを除いて)ほとんどなく、大半の来客が「すいません、どなたでしょうか(毎年この日だけ拝顔していますが、未だに貴方のお名前も素性も何も存じないんです)」状態で、その点は来訪される方々も同様でしょうから、互いに簡単に挨拶(お辞儀)をして終了、という程度のやりとりしかありません。
以前は実家に「来訪者チェックリスト(話題ネタ帳)を作って欲しい」と申し入れていたのですが、何年経っても行ってくれる気配がありませんでしたので「来訪の方々を把握しようとする努力」も諦めて、今は単なる挨拶ロボットになり果ててしまいました。
そんなこともあり「相方の実家にも行かなければならず、起案が山積みで仕事時間が1秒でも惜しい日々が続いているのに、こんな程度のことのために二戸くんだりまで丸一日来なければならないなんて」と無駄にイライラが募り、同行者とも無用の軋轢ばかり増してしまいます。
というわけで、子供の頃は「こんな家はイヤ」と思って飛び出した(近所を手短に放浪した)ことが珍しくありませんでしたので、今回も実家を少々家出することにしました。
で、まずは九戸城周辺に赴き、これまで歩いたことのないエリアを散策した後、穴牛大橋まで歩いて川又方面にUターンした後に実家まで戻ったので、約2時間半ほど、昼間の炎天下の中を散歩したことになりました。
久しぶりに訪ねた九戸城は、いつの間にか本丸の真下(盛岡地裁二戸支部から二の丸の入口までの地元民のための細い生活道路の付近)が整備されており、昔は畑だったところが遊歩道になっていました。ただ、それほどカッチリとした整備はされておらず、そばに少々の湧水が流れてヤンマ類の大型トンボも飛び交っていましたので、相応に爽やかな散歩道と言ってよいでしょう。
で、裁判所の建物のすぐ奥に整備(発掘?)された(昔は多分ありませんでした)道を通って正面部分(二の丸の中心エリア)に来たのですが、そのまま城を出るのも面白くないと思い、これまで立ち入ったことのない石沢館(北東の広場)エリアなどに立ち寄ってみました。
二の丸や本丸は、25年ほど前からの九戸城整備事業により「明るく爽やかな城址公園」になり、昔日の「荒城の月」そのものといった幽玄な様相がなくなってしまったのですが、石沢館はそのような整備(とりわけ地面の草刈りなど)がほとんどなされておらず、霊気あふれる雰囲気を残していたため、好ましく、また懐かしく感じました。
ただ、昔は、二の丸と石沢館の間にある細い道から白鳥川に下って川を渡り川又地区(福岡小学校や二戸市役所などの真下)に向かう小さな道があったのですが、残念なことに、この道が途中で途切れて白鳥川に下ることができなくなっていました。
小学3~4年の頃、人生に疲れたかどうかはさておき、何らかの理由で旧国道(通学路)に沿って帰宅するのが嫌で、この道を通って九戸城に行き、周辺を彷徨ってから帰宅する、ということが少なからずありました。
当時から「九戸城は、上方軍(秀吉・家康連合軍)に戦闘では負けなかったのに、謀略で騙されて城中皆殺しにされた怨念の宿る城」と認識しており、そうした特殊な空間に身を置くこと自体が自身の精神的な安定(回復)と何らかの形で結びついていたのではないかと思っています。
九戸城をざっと廻った後、山中に向かって穴牛大橋を目指しましたが、車ではあっという間に着く距離も歩くとさすがに長かったものの、久しく山登りから遠ざかっている身には「ジョギング好きの人がしばらく走らないと気分が悪くなる(ので、走るとスッキリする)」という感覚が分かるような気はしました。
途中には、田圃の道端にカモ(雁?)の群れが並んで座っている光景もあり、相応に癒やされました。
穴牛大橋を越えたあとは、割とあっという間に川又に戻ったのですが、折角なので白鳥川を見に行くことにしました。
最初に下りたところでは、対岸(川又側)に若干の護岸工事はあったものの、九戸城側は全く人の手が加えられておらず、森の中を渓流が音もなく静かに流れる姿を光がキラキラと包むような、幻想的な光景が広がっていました。
私にとって「日本で一番美しい渓流」は、山登りを始めたばかりの頃に渓谷途中で断念し引き返した、奥秩父の笛吹川東沢渓谷にある「千畳のナメ」だと思っているのですが、この日の白鳥川も水量が少なく川底がナメ状になっていたせいか、千畳のナメに少し通じるものがあるのではと感じました。
また、上述の「福岡小などから九戸城の二の丸に向かう道」も残っており(但し、橋を渡ってすぐに藪になり、そこから城には進めません)、周囲が鬱蒼としているため最初に下りた河岸ほどの美しさはありませんでしたが、相応に渓流美を感じることができる(少し整備すれば、できそうな)様相を呈していました。
九戸城は、四方(主に北面と西面)を断崖に囲まれているにもかかわらず、二戸市役所などには崖下の河川との繋がりを「景観形成(観光PR)としての城郭整備」に活かそうとする姿勢が感じられず、その点は残念に思います。
本丸や二の丸からは白鳥川は臨めませんが、石沢館からは白鳥川に真っ直ぐ落ちる断崖が藪の中に広がり、対岸(川又地区)に布陣した信直軍との在りし日の攻城戦などをイメージできそうな気もしました。
白鳥川は上流にダムもなく増水時には近寄ってはいけない川なのでしょうから、そうしたことも「廃道」の原因となっているのかもしれませんが、「川との繋がり(要害としての利用と、それに伴う中世末期の巨城としての壮観)があってこその九戸城」だと思いますので、二戸市役所などの関係者におかれては、白鳥川の景観を活かした九戸城の整備のあり方、という視点を大切にしていただければと思います。
というわけで、陳腐なキャッチコピーのような一首。
人生に疲れた貴方に九戸城 そして心を漱ぐ白鳥
九戸城は、近年盛んにPRされている「天下統一の最終戦」という位置づけだけでなく、岩手の人々にとっても「盛岡などはここから始まった」と言うべき場所であり、より多くの方に、その意義を理解していただければと思っています。
残念ながらカメラを持参せずに放浪したため写真を添付できませんが、ぜひ現地を訪れて体感していただければと思います。