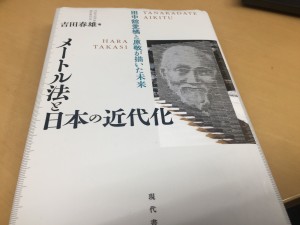函館ラ・サール中学に子弟が通学する保護者の方から「学校側に宣伝の努力が足りず、このままでは、盛岡の入試説明会(中学・高校共通)の来場者がゼロになりかねないので宣伝せよ」とのお達しを受けたので、勝手ながら以下のとおり告知させていただきます。
すいませんが宣伝目的(拡散希望)の投稿ですので、賛同いただける方はFacebookやTwitter等でご紹介いただければ幸いです。
また、私は断片的にしか拝見していませんが、こちらの「女性ユーチューバーの方(札幌のタレントさん?)の潜入・赤裸々インタビュー」が、現在の様子を知る上では大いに参考になるそうです。
以下、蛇足ながら関係者のはしくれとして多少述べさせていただきます。
*******
我が国では、数十年前から「大都会の子は、学業で身を立てたいなら中学受験し(今や東京では小学生の4人に1人と言われます)、地方の子は、公立中(か国立大付属中)→学力に応じた地元の公立高に入る」というのが当たり前の光景となり、これが現在まで延々と続いています。
関西圏は、主要三都に限らず、奈良など隣接県も私立中進学が珍しくないと聞いていますので、双方の境目は曖昧なのかもしれませんが、東北と関東では、この二つの社会の断絶が際立っており、あたかも二つの国家が併存しているようにすら見えます。
当然、その二つの社会の分断は、「現在の高偏差値大学の入学者は著名な私立中高一貫校の卒業生ばかりだ」という類の言説を取り上げるまでもなく、それぞれの社会の出身者の人生に強い影響を生じさせやすいであろうことは、相応に強く予測されるところです。
もちろん、田舎(地方)の家庭は、中学受験の光景を「子供は伸び伸び遊ばせてあげればいいのに勉強漬けの生活を強要され気の毒だ」と否定的に評価するのが通例でしょうし、私自身それが間違いだとは思いません。
また、素質のある子が幼少時に伸び伸びと暮らした後、公立中で猛勉強し盛岡一高などに進学して自身の志を実現していく光景も、大いに価値のあるものと認識しています。
ただ、曲がりなりにも「お受験」を経験した家庭としては、親子(主に母子)が圧倒的な努力を重ねて栄冠を勝ち取っていく(勝ち取ろうとする)経験を得ることは、常に言えるわけでないとしても、双方(とりわけ子)が、その後「努力を重ねて自身の希望を実現する人生を歩んでいく」上で、非常に貴重な経験になりうるということは、強調しても良いのではと感じています。
*******
ビッグコミックスピリッツに連載され、本年夏にドラマ化予定だった(今冬に放送?)「二月の勝者」という人気漫画は、「中学受験とは父親の経済力と母親の狂気だ」の一言から始まります。
のんびりと過ごしたい、ゲームを好きなだけ遊びたい子に、母親が通信教材を片手に悪鬼の如く勉強を強いる光景には、時に目を背けたくなるときもありますが、そうした関門を突き抜けることで、努力する習慣を身につけて学業で身を立てる力を得ていく子もいるということ、また、そうした経験を通じ子供のうちから学業での成功体験を得ることの価値は、地方に住む方々も、理解いただいてよいのではと思われます。
地方在住者も、運動関係であれば、いわゆる「アスリート・エリート」のご一家などが親子一丸となって特定のスポーツに凄まじい努力を重ねる光景を見聞することがあります。それとの比較からも、「お受験」だけが特異というわけではなく、勉強分野で幼少の子と親が一丸となって努力すること(その経験を得るものとしての中学受験)は、少なくとも適性がある家族なら経験する価値は相応にあるのではと思われます。
要は、地方で育児に従事するご家庭も、「伸び伸び育てて、公立中→公立高へ」という地方では当然の(ごくノーマルな)生き方だけでなく、小学4~5年生頃から上記の「モーレツ体験」という選択肢も視野に入れ、あとは、お子さんの適性やご家庭の事情などに応じて、どちらにするか決めていただければよいのでは、少なくとも、後者に適性を有する子から地方在住というだけでその選択肢を奪うのは間違っているのではないかという点は、皆さんにも考えていただきたいところです。
*******
その上で、次のテーマとして「函館ラ・サールという選択肢」について少し述べたいと思います。
ご存知の方も一定数おられるかと思いますが、この学校は、函館在住の子は自宅から通学しますが、それ以外の地域の出身者は、ほとんど全員(中学は必須)が寮生活を送ります。
以前に投稿したこともありますが、中学3年間(及び高校入学者の1年間)は二段ベッドとロッカーが並ぶ大部屋での寝泊まりが必要になり、他の寮生と両立して生活するため社会性(一定の社交性)の鍛錬を余儀なくされるという点でも、特異な面があります(このような手法は、全国でも同校だけかもしれません)。
親から見れば何かと気の毒に感じる面はありますが、子にとっては相応に大過なく生活できており、「物事は案外なるようになるものだ」と感じる面があります。
また、中学生になれば、もはや身長に限らず自我のかなりの面で大人と大差ないレベルになってくる、そうであれば互いに一定の距離をとった方が、双方のため、とりわけ子にとっては自立心などの涵養の上で望ましいのではないかとも感じます。
******
以前読んだ橘玲氏の「言ってはいけない」(新潮新書)で、親が子に影響を与えることができるのは幼少期の限られた期間だけで、その後は主として同世代から影響を受ける面が大きいと述べているのを見た記憶があります。それが正しいのであれば、函館ラ・サールで、全道・全国から集まる「学業で身を立てたい同級生達」から良好な影響を受けることができれば、本人のその後に強い威力を発揮するのかもしれません。
逆もまた然りで、多少存在するかもしれない残念な同級生に残念な影響を受けないよう願うばかりですが・・
余談ながら、この仕事をしていると、大人になっても長く同居する親子が残念な寄生関係に陥った結果、好ましくない事件が起きる例を拝見し、「この人達は何年も前から離れて暮らせば良かったのに」と感じることが多々あります。子が親と離れて暮らすことの意義や価値に、もっと光が当てられてもよいのかもしれません。
また、昔と今で生徒の出身地の比率に多少の違いがありますが(昔は道東など北海道の小都市や辺境の出身者が中心で今は東京などが多い)、全国の各地から子供達が集まってくる珍しい学校であることに変わりなく、その点=擬似的な上京体験という点でも、お子さんに得がたい体験をさせることができる面はあります。
そもそも、子を未熟なうちから外の世界に出して鍛錬させることは岩手でも昔から相応に存在した光景です。
明治=戊辰敗戦後の世で言えば、二戸出身の田中舘愛橘(日本物理諸科学の創設者の一人)は、若年時に親が自宅を売り払い一緒に上京してまで最先端の学問を習得させ、言わずと知れた原敬も、同時期に上京し司法省法学校などで研鑽し、その後の飛躍につなげています。
それら偉人に及ぶかはさておき、岩手の方々にも、函館ラ・サールという選択肢は、そうした先人が辿った道に通じるものがあるのかもしれないという視点を、持っていただければ幸いに思います。
*******
かくいう私も、30年以上前、盛岡一高と函館ラ・サール高校の双方に、どういうわけか(受験者の実感として双方とも間違いなく最下位ランクで)合格してしまい、一体どちらに進学すべきかという身の程を超えた悩みを抱えたことがあります。
その際、最後の決め手になったのは、一高にプールがあってラ・サールには無かったから・・・ではなく、また、運動できない「のび太」なので高校時代に男女交際できる自信はなかったから・・・でもなく、自分は将来、盛岡を拠点に、岩手の人と社会のため生きたいと思うのではないか、そうであれば今のうちに外の世界を見ておくべきだとの「うすうす感」があったことでした。
自身の高校時代に未熟さゆえに悔いる点は山ほどありますが、その判断自体については、私自身の問題として後悔する点は何一つありません(反面、一高には今も「最下位レベルで拾っていただいたかもしれないのに、すいません」という申し訳ない思いで一杯で、一高OBばかりの盛岡の社会では、いつも肩身の狭い思いをしています)。
皆さんも、私のようなケースに限らず「うちは子供に家業を継いで欲しい」などの事情のある方もおられるかと思いますが、そうした大人になれば岩手で人生を送る可能性の高い方ほど、若年時に外の空気を吸っておくことに、意味や価値があるのではと感じます。
また、函館ラ・サール中学にご子息を通学させる方の中には「若い頃から、外の空気を吸って、世界全体に目を向けることを考えて欲しい」という理由で送り出す方も少なくないようです(それが奏功して、お子さんも海外留学などの希望を持っておられるという話を聞いたことがあります)。
私が入学した当時は、科目全般なかんずく数学や理科が「田舎の公立中で教えている内容」との難度差があまりにも大きく(断崖絶壁のような落差でした)、私自身はそれに嵌まって入学直後から落伍してしまい、文系分野では若干の持ち直しはあったものの、全体的にパッとしない成績のまま高校を終えました。
ただ、一緒に寮生活(とりわけ、2、3年次の4人部屋)で過ごした仲間が、圧倒的かつ規則正しい勉強生活を続け、その結果、難関大(医学部・医科大)に現役合格していく光景をよく見ており、その背中を見続けていたことが、司法試験に(当時としては、あまりにも運良く)大卒2年目で合格できた、大きな原動力になりました。
もし、皆さんのお子さん・お孫さんも「地元の公立高もいいけど、敢えて、そんな環境に放り込んでみたい」とお考えになるのでしたら、函館ラ・サールという選択肢も考えていただければ幸いです。
*****
もちろん、私立中の寮生活ですので一定の経済的負担はありますが、カトリック系の学校だからか?昔(私の時代)から同校の学費や寮費はさほど高額でなく、三食・風呂・洗濯などが完備されていることも含め、東京の大学に通学し生活する学費などに比べると、金額はかなり低い(良心的)と思われます(反面、寮の食事に関しては・・以下、自粛)。
facebook等ではゴルフや会食など華やかな暮らしをなさっている方々の姿も拝見することがありますが、そうした皆さんが、若干でも、若い世代の学業のためにお金を投資していただければと思っています。
皆さんの子弟に、私たちの新たな仲間に加わっていただける日を心待ちにしつつ、最後までご覧いただいた方に御礼申し上げます。
R04.8追記
本年、一度、寮の食事をいただく機会がありましたが、私の時代=30年前と比べて、寮の食事はかなり質が向上したのでは?と感じる面はありましたので、念のため付記しておきます(そのとき限りなのか否かは存じませんが・・)。